ゴルフを始めて少し慣れてくると、「もっと飛距離を出したい」「風のある日でも低く安定した球筋で打ちたい」と思うことがありますよね。
そんなゴルファーにおすすめしたいのが、直ドラというテクニックです。
しかし、「直ドラは禁止なの?」「どうやって打てばいいの?」「しやすいドライバーは何?」など、疑問や不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
私もゴルフを始めて数年経ちますが、直ドラはスコアアップだけでなく、自分のスイングを見直す絶好のチャンスを与えてくれました。
この記事では、直ドラのルール上の扱いや、直ドラしやすいおすすめドライバー、直ドラならではのメリット、成功率を高める打ち方のコツまで、実体験と専門的な観点を交えて詳しく解説します。
きっと地蔵に興味がある。あなたの疑問や悩みもすっきり解決します。
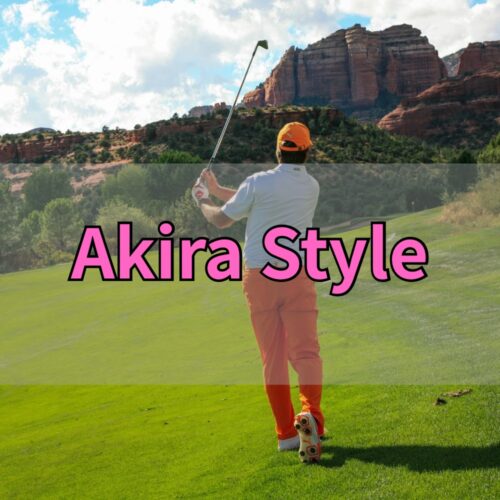
ゴルフ場勤務で月2~3回ラウンドしています。
日々の業務を通じてゴルフの魅力を広めることに情熱を注いでいます。
豊富な経験を活かし、初心者から上級者まで幅広いゴルファーに向けた情報を提供しています。
ゴルフに関する知識を深めるため、常に最新のトレンドや技術を学び続けています。
直ドラは禁止なの?疑問をスパッと解決!
直ドラとは、ティーアップせずに地面に直接置いたボールをドライバーで打つ技術です。
結論からお伝えすると、直ドラ自体がゴルフのルールで禁じられていることはありません。
競技ゴルフの公式ルールでも、ティーアップしなければならない決まりはなく、ラウンド中でもティーショット以外でドライバーを使って打つことも認められています。
ただし、練習場によっては「直ドラ禁止」としているところがあります。
その理由として一番大きいのは、ドライバーのソールやフェースが地面と接触しやすく、クラブが傷つく可能性が高いからです。
また、マットが傷みやすいといった施設側の都合もあります。
ですから、ダメージを避けたい人や、練習場のルールを守りたいという人は、事前に必ずスタッフに確認しておくことをおすすめします。
私もこれまで複数のゴルフ練習場で直ドラを試みたことがありますが、直ドラは禁止と明記しているところもあれば、特に何も言われなかったところもありました。
クラブの性質上、どうしてもダメージのリスクは高まりますが、上達の幅が広がる貴重な練習方法だと実感しています。
特にドライバーが苦手と感じている人は、直ドラ練習でスイングの見直しやボールのとらえ方の改善に繋がることが多いので、自分のゴルフの幅を広げたい方にはチャレンジしてみてほしいと思います。

ただし、練習場独自のルールやるだけは絶対無視しないようにしましょう。
直ドラしやすいドライバーとは?自分に合った一本が見つかる選び方
直ドラはボールをティーアップしない分、クラブに求められる条件がいくつか出てきます。
ポイントは「低重心設計」と「シャローフェース」。
低重心設計のドライバーは重心位置がヘッド下部にあり、ボールが上がりやすいため、地面からでも適切な弾道に持っていきやすい特長があります。
シャローフェースとは、フェースの高さが低めで、芝や地面の影響を受けにくいクラブを指します。
おすすめドライバー5選を紹介
おすすめドライバー5選を紹介します
短尺で振り抜きやすく、低重心設計が特徴。
シンプルでシックなデザインで、ミート率を上げたい人におすすめです。
スピンや打ち出し角を補正し、曲がりにくい弾道を実現。
大きなミートスポットで、安定したショットを求めるゴルファーに最適です。
高い直進性と初速アップを実現した設計で、特に初心者や女性におすすめ。
軽量で扱いやすく、安定したショットをサポートします。
特にシャローフェースは、フェアウェイウッドのような感覚で使えるので、直ドラ入門にも最適です。
私自身、直ドラを楽に打ちたいと感じてからドライバー選びにすごくこだわるようになりました。
色々なクラブを打ち比べた結果、低重心&シャローフェースのモデルを選ぶことで、明らかにボールの浮き上がりやすさに差が出ます。
特にややスイートスポットが広いモデルは、ミスヒット時にも安定した球が出やすく、直ドラへの心理的なハードルもかなり下がります。
もし新しいドライバーを検討している方や、直ドラ専用にもう1本用意したいと言う方は、ショップの試打コーナーで、ぜひ低重心・シャローフェイス仕様を打ち比べてみる価値がありますよ!
直ドラのメリットと成功する打ち方のコツを紹介
直ドラのメリットは、単に飛距離がよく出るだけではありません。
私の実践経験や周囲の意見も踏まえて、特に効果的だと感じるメリットを挙げます。
直ドラはボールがティーアップされていないため、アッパースイング(下からすくい上げるような軌道)ではミスショットになりやすいです。
そのためダウンブロー気味の安定したインパクトを意識するようになるため、自然とスイング精度が高まります。
私自身、直ドラの練習を始めてからアイアンやウッドショットも格段に良くなりました。
直ドラは、強風の際でも球筋がふらつきにくい低弾道ショットが打ちやすくなります。
これは風の強い日のセカンドショットなど、局面によって大きなアドバンテージとなります。
普段からフェアウェイウッドが苦手という方も、直ドラが使えればコース攻略の幅が一気に広がりますよ。
私が最も大きな価値を感じているのは、メンタル面の強化です。
直ドラは難度が高い分、うまく打てた時の達成感が格別ですし、難しい練習を日常的に行うことで本番のプレッシャーにも強くなります。
成功体験がゴルフ全体の自信につながります。
直ドラは難易度が高いといわれますが、ちょっとしたポイントさえ押さえればしっかり成果が出るはずです。
いきなりフルスイングするとミートが難しくなるため、まずはハーフスイングや7~8割のスイングでボールを芯に当てる感覚を養いましょう。
この反復がインパクトの安定に直結します。
スタンス幅の中央より少し左足寄り(右打ちの場合)に置くのが基本です。
こうすることでダフリを防ぎ、クラブのロフトでしっかりボールをとらえられます。
打ち込むよりも横から払うイメージでスイングし、芝やマットを削りすぎないように注意しましょう。
ドライバーが地面に引っかかる感覚がある場合は、スイング軌道やフェース角を調整してみてください。
もし頻繁に直ドラにトライしたい場合、多少傷がついても気にならない中古クラブを1つ練習用として持っておくのも賢い選択です。
直ドラ体験談を紹介
実は、先日のラウンドでどうしても直ドラを試したくて、ロングホールで思い切ってチャレンジしました。
グリップを普段より少し短く握って慎重にセットアップ。
すると、まさかの会心の一撃!
なんとそのロングホールは2オンに成功して、同伴者からもどよめきが。
これは、これから俺の新必殺技になるかも?
とすっかり調子に乗ったんですが、次のロングホールはそう簡単にいかず、打ち込んだ瞬間ダフってチョロ…。
やっぱり直ドラは一筋縄ではいきません。

成功体験と失敗が続けてやってきて、このゴルフの奥深さがたまらなく面白いと実感した一日でした。
記事のまとめ
直ドラは、一見上級者向けの特殊なテクニックのようですが、ゴルフ技術とメンタルの両面を鍛えるうえで非常に有効な練習方法です。
「直ドラは禁止なの?」という疑問も、ゴルフルール上は許可されているので安心してチャレンジできます。
ただし、練習場のルールやクラブへのダメージには気を付けてください。
直ドラしやすいドライバー選びでは「低重心設計」「シャローフェース」が重要なキーワードです。
クラブ選びやスイング調整のヒントをぜひ参考にしてください。
直ドラを通して得られるメリットは、スコアだけでなくメンタル面やショット精度の向上にもつながるので、自信を持ってチャレンジしてほしいと思います。
ゴルフは本来楽しむものです。
直ドラという新しいテクニックに挑戦することで、あなたのゴルフがもっと自由に、面白く、そして上達していくはずです。
疑問や悩みが解消できたら、ぜひ一度コースや練習場で直ドラにトライしてみてください。
ゴルフ人気商品
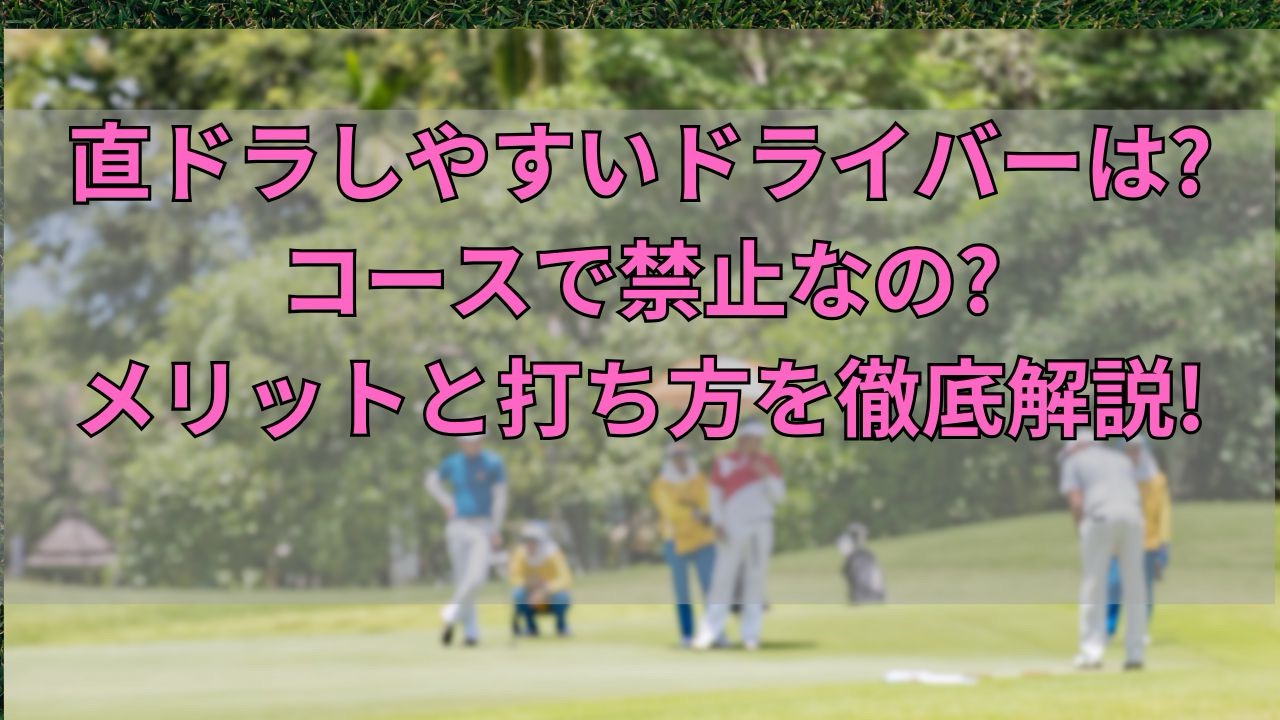












コメント